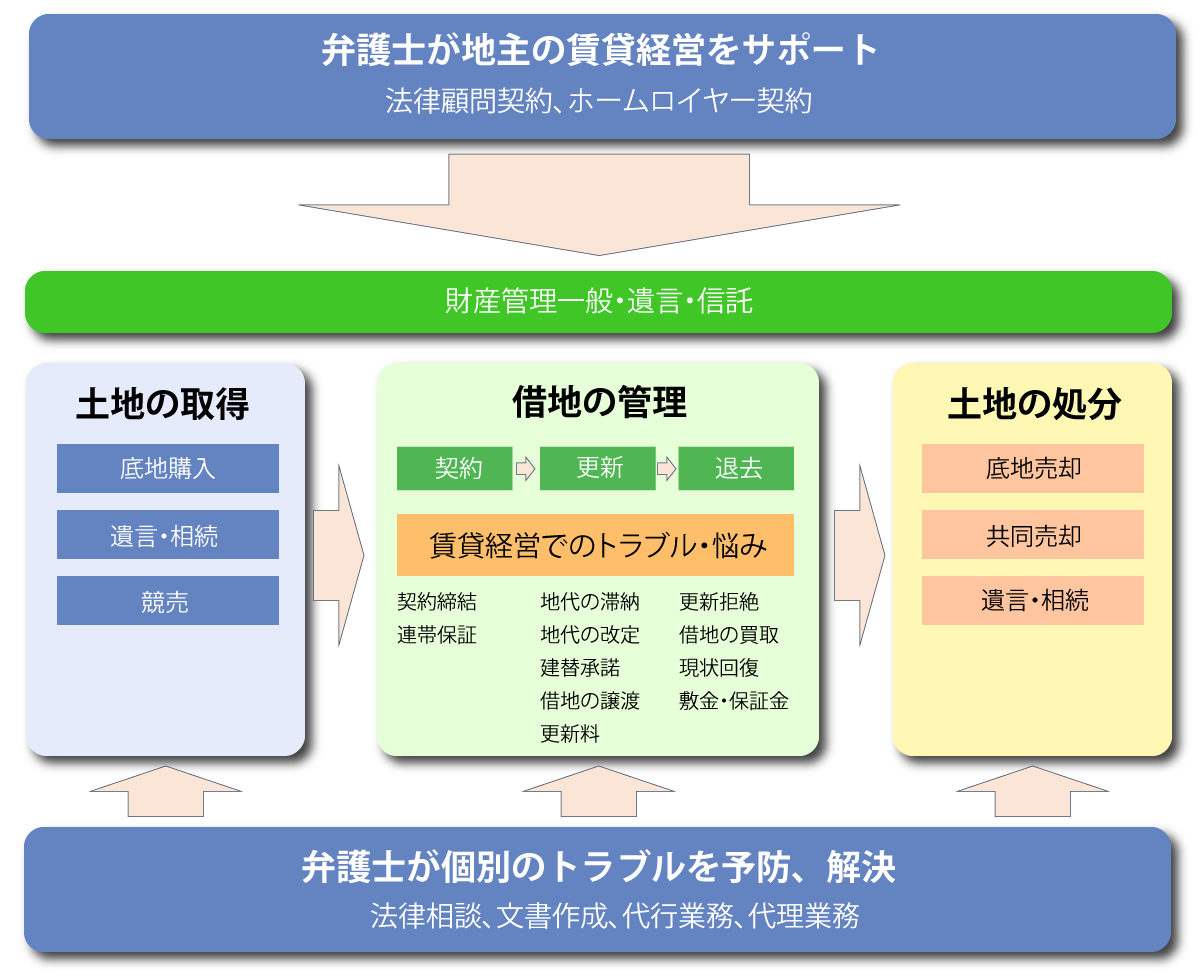
土地賃貸に関するよくある質問
- 紹介がなくても相談できますか。
- ご紹介は不要ですので、お気軽にご相談下さい。
- 本人に代わって代理で相談できますか。
- 相談は可能です。ご家族の方や取扱業者の方によるご相談にも対応しております。 但し、その後当事務所で受任する際には、本人に面会して意思確認をさせていただく必要があります。 また、法律相談についても直接ご本人から詳細を伺うことができないため、正確なアドバイスが行えない可能性があります。 なお、特殊な事情がある場合には、弁護士が本人のもとへ赴くことも可能ですので、ご相談下さい。
- 土日や平日夜間でも相談できますか。
- 原則として、ご予約いただける相談開始時刻は、平日の9時00分から17時30分までとなります。 もっとも、お勤めの方などお時間が取れない方については執務時間外の対応も可能ですのでご相談ください。
土地賃貸に関するご相談例
- 「旧法借地」と「新法借地」
「旧法借地」、「新法借地」とは何でしょうか。
- 「新法借地」とは、現行の借地借家法が施行された平成4年(2001年)8月1日以降に新しく成立した借地権のことをいいます。「新法借地」には借地借家法が適用されます。
これに対し、「旧法借地」とは、平成4年(2001年)8月1日よりも前に成立した借地権をいいます。
旧法借地にも「特別の定めがある場合を除き」借地借家法が適用されるものとされていますが、借地の更新後の契約期間などについては、旧法である借地法の適用を受けることになります。契約期間には、以下のような違いがあります。■「新法借地」の場合
新規契約時 30年(契約でこれより長い期間を定めることは可能)
最初の更新後 20年(同上)
その後の更新後 10年(同上)■「旧法借地」の場合
新規契約時・・・堅固建物について30年以上(定めがなければ60年)
非堅固建物について20年以上(定めがなければ30年)
更新後・・・堅固建物について30年(これより長い期間の定め可)
非堅固建物について20年(同上)
※堅固建物の例:鉄筋コンクリート造りの建物
非堅固建物の例:木造建物
- 借地権価格の算出方法
譲渡承諾料などの交渉の際に基準とすべき「借地権価格」はどのように算出すればよいですか。
- 以下のような方法があります。
1.公示地価や基準地価を参考とする方法
(1) 公示地価
公示地価とは、地価公示法に基づいて、適正な地価の形成のために国によって公示される価格です。
国交省によって、毎年3月にその年の1月1日時点の価格が公表されます。
不動産鑑定士による鑑定に基づいていますので、その土地の「時価」に最も近いといえます。
もっとも、標準地毎の価格が示されるのみであり、すべての土地の価格が直ちに明らかになるものではありません。
(2) 基準地価
これと類似のものとして、都道府県によって示される基準価格というものもあります。
国土利用計画法施行令に基づいて、都道府県知事が毎年9月頃にその年の7月1日における標準価格を公表するものです。
公示地価と基準価格は、いずれも国土交通省の「土地総合情報システム」(https://www.land.mlit.go.jp/webland/)で確認できます。
(3) 借地権価格の算定
借地権の価格は、これらによって得られた更地価格に借地権割合を乗じて得ることができます。
借地権割合は、後記の相続税路線価図に示された借地権割合(A~G)が参考となります。2.相続税路線価を参考とする方法
相続税路線価(単に「路線価」というときは、この相続税路線価を指すことが多い)とは、相続税や贈与税を計算するための財産評価基準のことです。
国税庁によって、毎年7月1日にその年の1月1日時点の価格が公表されます。
国税庁のサイト(https://www.rosenka.nta.go.jp/)で確認できます。
路線(道路)ごとに、そこに面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位)が表示されています。
また、路線毎にA(90%)~G(30%)の借地権割合が示されています。
これを用いて、以下の計算でおおよその借地権価格を求めることができます。当該土地の路線価(円)×広さ(㎡)×借地権割合(%)=借地権価格
※厳密には地形等による補正があります。
なお、一般的には、路線価は、公示地価(地価公示価格)の80%程度となっていることが多いです。
そのため、上記で求めた価格を80%で除した額(又は1.25倍した額)を参考にすることもあります。3.不動産業者に簡易査定を依頼する方法
上記の各指標や実際の取引事例を元に、不動産業者に想定される販売価格を査定してもらう方法もあります。
もっとも、譲渡や建替に対する地主の承諾を要する(時間やコストがかかる)等の特殊性もあり、流通性も低いため、上記1,2で求めた数値よりもかなり下回る査定がなされることも少なくありません。4.不動産鑑定士に鑑定してもらう方法
裁判になっているなどして当事者双方で借地権の評価方法・価格に意見の相違がある場合には、不動産鑑定士に鑑定してもらう方法も考えられます。
また、借地非訟手続では裁判所から選任された鑑定委員会(不動産鑑定士等の専門家で構成)が借地権の価格等について意見を出すこととされています。
もっとも、自ら鑑定を依頼する場合には、費用がかかります(鑑定委員会の費用は不要ですが、あくまでも借地非訟手続内の制度です)。以上のとおり、借地権の評価の仕方にはいろいろな方法がありますが、それぞれメリット、デメリットがあります。
どれが正解というわけではなく、場面場面に応じて、上記をうまく使い分けていくことになります。
- 借地権の無断譲渡か(相続)
借地人が死亡し、その長男が借地上の建物を相続し、既に登記もされています。
(1) 無断譲渡として、契約を解除できますか。
(2) 名義書換料を求めることはできますか。
(3) 契約書を作り直す必要はありますか。
- 1.(1)について(契約解除の可否)
相続の場合、相続人は被相続人の借地人としての権利義務を包括してそのまま承継することになり(包括承継)、無断譲渡とはなりません。
従前の契約関係がそのまま引き継がれることになります。
したがって、無断譲渡とはならず、契約を解除することはできません。2.(2)について(名義書換料請求の可否)
上記のとおり、相続人が当然に被相続人の賃借人の地位を引き継ぐことになりますので、名義書換料を求めることもできません。3.(3)について(契約書作成の要否)
上記のとおり、相続人が当然に被相続人の賃借人の地位を引き継ぐことになります。
借地人は地主に対して新たに契約書の作成の義務は負いません。
もっとも、従前の契約内容を確認する意味で、借地人同意のもとで改めて契約書を作成する例はあります。
- 借地権の無断譲渡か(遺贈)
借地人が死亡しました。
借地人には相続人はおらず、遺言によって、生前借地人の世話をしていた者が借地上の建物を取得したようです。
無断譲渡として、契約を解除することはできますか。
- 1.遺言により財産を譲る行為を遺贈といいます。
遺贈には、遺産のすべてを対象とする包括遺贈と、特定の財産について行う特定遺贈があります。2.包括遺贈がなされた場合、「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する」とされていますから(民法990条)、相続による取得の場合と同様に、そもそも地主の承諾は不要との解釈が成り立ち得ます。3.また、仮に形式上無断譲渡と解される場合にも、解除が認められないケースがあります。
契約違反があっても、「賃借人の当該行為が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情」がある場合には、契約解除はなしえないというのが判例の考え方です。
当該受遺者が長年連れ添った者である等の事情がある場合には、契約解除は認められない可能性があります。4.参考裁判例として以下のようなものがあります。
東京地裁平成19年7月10日判決は、
「被告(包括受遺者)は,B(借地人)の甥であり,Bの遺言によりその全財産の包括遺贈を受けた者である。また,Bが全財産を被告に遺贈する旨の遺言をしたこと自体から,被告とBが親密な関係にあったことを推認することができる。そして,相続による包括承継であれば賃貸人の承諾は不要と解されるところ,包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有すること(民法990条)に照らすと,本件においてBから被告への本件借地権の承継につき原告の承諾が必要であると解すべき実質的理由は乏しく,むしろ,形式的に承諾がないことをもって原告の被告に対する建物収去土地明渡請求を認めることは相当でないと考えられる。」とした上、「本件においては,本件借地権の譲渡が原告に対する背信行為に当たると認めるに足りない特段の事情があるから,原告による本件賃貸借契約の解除は認められないと判断するのが相当である。」としています。
- 借地権の無断譲渡か(借地上の建物の賃貸)
借地人が借地上の建物を無断で第三者に賃貸しています。
借地を無断で転貸するものとして契約を解除できますか。
- 実務においては、特段の事情がない限り、借地上の建物の賃貸は借地の転貸にはあたらないと解されています。
借地権は借地人の建物所有のために設定されるものであり、借地人は自分が建てた建物は自由に使用収益することができます。
その一環として、第三者に対して建物を賃貸することも許されると解されています。
建物が賃貸された場合に建物賃借人が敷地を使用することにはなりますが、これは建物利用に付随するものであり、土地の転貸とまでは解されません。
古い判例ではありますが、「土地の賃借人がその地上に建設したる建物を賃貸し、その敷地としての土地の利用を許容する場合の如きは、これを土地の転貸借と目すべきものにあらざる・・・」としたものがあります(大審院昭和8年12月11日判決)。


